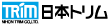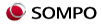地域とともに走る"プレイングワーカー" FCふじざくら山梨が鳴沢村で築く新しいクラブ像
【鳴沢村に広がる笑顔とつながり】
山々に囲まれた鳴沢村では、村のあちこちが笑顔と声で満たされる日がある。
屋内テニスコートで開かれるサッカー教室では、ボールを追いかける子どもたちが選手の名前を呼びながら駆け寄り、武道館では軽運動レッスンの参加者が笑い合いながら体をほぐす。小学校の体育館では、アクティブスクールに夢中になる子どもたちの姿も見られる。また、不定期で行われるヨガ体験では、広場に集まった大人たちが呼吸を整え、心身をリフレッシュさせる。
会場やプログラムは回ごとに異なるが、変わらないのは、FCふじざくら山梨の選手たちが村の人々と向き合う姿勢だ。初めて顔を合わせた日から少しずつ築かれてきた信頼関係は、今では「また来てくれたんだね」と笑顔で交わす間柄になった。活動を単発で終わらせず、繰り返し訪れることで生まれるつながり。その継続性こそ、クラブと地域が築いてきた信頼関係が根づく最大の理由だ。

【地域と競技をつなぐ"プレイングワーカー"】
FCふじざくら山梨はクラブの理念として「プレイングワーカー」の育成を掲げている。地域活動においても、現役選手たちが自ら企画・運営し、主体的に取り組むことを求めている。事業担当者の三津谷翔平氏は、自律的な活動のあり方についてこう説明する。
「選手には常に『自分たちで課題を設定し、改善してほしい』と伝えています。サッカー教室を担当する辻野友実子は、当初はメインコーチとして練習メニューを考えていましたが、今は後輩選手にその役割を任せ、自らはチェックやフィードバック役に回っています。こうして選手同士で運営できる仕組みを整えています。『競技でも一流、社会でも一流』を目指す理念を体現してくれています」
活動は会社のプロジェクトのように進む。半年に一度のミーティングで方向性を決め、「自分のファンを増やす」「指導力を高める」「子どもたちにサッカーの楽しさを伝える」など、各自が目標を設定。例えば、ファンを増やしたい選手は「輪に入りづらい子どもをサポートする」、指導力を磨きたい選手は「全体指導を担当する」など、目的を持って参加している。
この「自走する組織づくり」は競技面にも通じている。
「選手主導でおこなっている取り組みですが、スポーツ選手である以上、引退や退団に伴い入れ替わりが起こることもあるので、属人化しない仕組みづくりは意識しています。ただし同時に、"属人化するほど自分のファンを増やしてほしい"とも思っています」(三津谷氏)
クラブに長期間在籍している選手が新加入選手をサポートする「メンター制度」により、取り組みは世代を超えて継承されている。準備から運営、振り返りまで主体的に関わり、競技力向上と並行して社会でも力を発揮する――それが「プレイングワーカー」の本質だ。
【鳴沢村との出会いが生んだ継続の力】
標高1,000メートルを超える高原の村、鳴沢村。富士山を望む雄大な景色に囲まれ、人口は約3,000人の村だ。かつては子どもや働き盛り世代が日常的に運動に触れる機会は限られていたが、現在はFCふじざくら山梨との連携により、多様な企画によって運動の機会づくりが進められている。
事業担当者の三津谷氏は、村との協働の経緯をこう説明する。
「鳴沢村さんとは『一緒に街を盛り上げましょう』という包括協定を2022年に結び、教育委員会と連携してサッカー教室からスタートしました。その後、福祉保健課とも話を進め、村の健康調査で明らかになった課題に対応するため、大人向けの軽運動を始めました。子どもたちがスポーツクラブに入らずとも気軽に運動できる場をつくるため、小学生対象のサッカー教室及びアクティブ教室は月1回ずつ、大人向け軽運動は年2回のイベントから始まり、今では月1回の定期開催と年1回のイベントに発展しています。継続しなければ変化は見えないので、単発開催はせず、すべての活動で継続性を重視してきました」
教育委員会では、小学生の運動能力向上や運動習慣づくりを目的にFCふじざくら山梨に協力を依頼し、令和4年からサッカー教室を開始。令和6年度からはレクチャー要素を取り入れたアクティブ教室も継続している。教育委員会の堀内仲氏は、こうした取り組みが村にもたらした効果を語る。
「運動能力の向上だけでなく、スポーツに触れるきっかけや地域チームを知る場にもなっています。選手やコーチとの触れ合いから新しい関係や興味が生まれ、人間的な成長にもつながっています」

一方、福祉保健課保健師の渡邊葉子氏は、健康づくりの観点からチームとの協働を進めてきた。
「住民アンケートでは、高齢者は比較的運動習慣がある一方、20〜69歳の約6割がほとんど運動していないという結果が出ました。そこで、働き盛り世代向けの教室を企画してもらいました」
サッカー教室で選手が子どもたちと交流する選手の姿を見ていたことが、大人向け事業を依頼する後押しになったという。活動はサッカーにとどまらず、ヨガや軽運動など多様なプログラムに広がった。「サッカーに興味がなかった世代でも、選手と一緒に体を動かすことでチームにも関心を持つ方が増えました」と渡邊氏。ヨガは親子や祖父母世代の参加も多く、世代を超えた交流の場にもなっている。
こうして年を重ねるごとに、活動は年々定着し、鳴沢村におけるスポーツ文化の土台を築きつつある。
【地域と向き合い、選手も成長する】
地域活動はクラブの理念を体現する場であると同時に、選手個人にとっても学びと成長の機会となる。サッカー指導に加え、健康づくりや生活習慣の改善にも関わることで、競技生活だけでは得られない経験を積むことができる。
辻野友実子は、2022年から鳴沢村の小学生を対象にした定期サッカー教室を担当。月2回のうち1回は選手たちが練習メニューを考え、直接指導している。大学時代から続けるサッカーの教室の経験を活かし、子どもたちの運動不足解消や"運動が楽しい"という感覚を持ってもらうことを目的に始め、今年で4年目を迎えた。
「最初はボールにも触れなかった子が積極的にゴールを狙う姿を見ると嬉しくなります。楽しみながら上手くなる練習を考えることがやりがいです」と辻野は手応えを口にする。「スポーツが苦手だったけど、サッカーをやってから楽しくなりました」と綴られた、女の子からもらった手紙は宝物だ。活動を通じてホームゲームにも応援に来てもらえるようになり、「個人としても結果を出したい」という思いが強まっているという。

一方、福祉保健課保健師の渡邊葉子氏は、健康づくりの観点からチームとの協働を進めてきた。
「住民アンケートでは、高齢者は比較的運動習慣がある一方、20〜69歳の約6割がほとんど運動していないという結果が出ました。そこで、働き盛り世代向けの教室を企画してもらいました」
サッカー教室で選手が子どもたちと交流する選手の姿を見ていたことが、大人向け事業を依頼する後押しになったという。活動はサッカーにとどまらず、ヨガや軽運動など多様なプログラムに広がった。「サッカーに興味がなかった世代でも、選手と一緒に体を動かすことでチームにも関心を持つ方が増えました」と渡邊氏。ヨガは親子や祖父母世代の参加も多く、世代を超えた交流の場にもなっている。
こうして年を重ねるごとに、活動は年々定着し、鳴沢村におけるスポーツ文化の土台を築きつつある。
【地域と向き合い、選手も成長する】
地域活動はクラブの理念を体現する場であると同時に、選手個人にとっても学びと成長の機会となる。サッカー指導に加え、健康づくりや生活習慣の改善にも関わることで、競技生活だけでは得られない経験を積むことができる。
辻野友実子は、2022年から鳴沢村の小学生を対象にした定期サッカー教室を担当。月2回のうち1回は選手たちが練習メニューを考え、直接指導している。大学時代から続けるサッカーの教室の経験を活かし、子どもたちの運動不足解消や"運動が楽しい"という感覚を持ってもらうことを目的に始め、今年で4年目を迎えた。
「最初はボールにも触れなかった子が積極的にゴールを狙う姿を見ると嬉しくなります。楽しみながら上手くなる練習を考えることがやりがいです」と辻野は手応えを口にする。「スポーツが苦手だったけど、サッカーをやってから楽しくなりました」と綴られた、女の子からもらった手紙は宝物だ。活動を通じてホームゲームにも応援に来てもらえるようになり、「個人としても結果を出したい」という思いが強まっているという。

【村・クラブ・選手 三者で作る"協働の場"】
活動は、村が会場や広報を担い、クラブが企画と実行力を提供し、選手が場を盛り上げるという三者協働で成り立っている。
堀内氏は、「小学生の健康増進と習慣化が目標でしたが、多い時には小学生30人以上の参加がありました。全校で約140人なので、割合としても高く、成果を感じています」と言葉に力を込める。定期的に顔を合わせることで、子どもたちの運動習慣が自然に身についてきたという。
大人向け軽運動レッスンは、参加者の多くが日常的に運動をしていない層だ。働き盛り世代の参加を促すため、サッカー教室と同時間帯に隣の会場で行っているが、午後7〜8時は忙しい時間帯とあって参加者数は伸び悩んでいる。それでもリピート率は高く、改善の余地と可能性が同居している。渡邊氏は、その現場を間近で見守りながら、成果と課題の両面を感じ取ってきた。
「大森選手のキャラクターや、行政とは違った企画力で住民に楽しさを提供してくれます。参加者同士のつながりが生まれるのも大きく、行政の健康教室とは全く違う雰囲気で、楽しみながら体を動かせる場になっています。働き盛り世代にももっと参加してもらえるよう、時間帯や運営方法は改善していく必要も感じています」
事業担当者の三津谷氏も、村とクラブが一緒に成長している協働の手応えを感じている。継続によって子どもたちの技術向上が目に見えるようになった一方で、レベル差への対応や、より多くの村民に参加してもらうための工夫が今後の課題だ。「まだ参加していない層も多いので、さらに広く、継続的に来てもらえるよう改善していく必要があると思います」と、プログラムや対象の拡大を視野に入れている。
【鳴沢村から広がる未来図と選手の思い】
三津谷氏は、サッカー教室から始まった活動を、大人向けプログラムや学校の社会科見学などへと発展させ、鳴沢村での取り組みを「点から面へ」と広げる構想を描く。
「地域全体でチームを応援する風土ができて、来場者が増え、選手のモチベーションが上がり、結果につながる──そんな好循環を生み出すのが理想です。一つひとつの取り組みを積み重ねながら、クラブとして着実にステップアップしていきたいです」
クラブは富士吉田市など他の市町村とも包括協定を結び、昨季からは甲府でのホームゲーム開催も始めた。今季は試合数を増やし、同様の地域活動を少しずつ展開していく予定だ。
大森みさきは、「このイベントをきっかけにクラブを知り、『応援しに行ってみようかな』と思っていただけたら嬉しい」と語り、辻野友実子は、「地域の方々に夢や元気を与えられる存在でありたいです」と抱負を述べた。
村・クラブ・選手が顔の見える関係を築き、関わり合い、応援が生まれる。この循環こそが、FCふじざくら山梨が目指す地域密着型クラブの姿であり、鳴沢村から全国へと広がる可能性を秘めた協働の輪である。
文=松原渓(スポーツライター)
 一般社団法人日本女子サッカーリーグ
一般社団法人日本女子サッカーリーグ