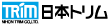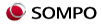誰もが楽しめるスタジアムへ 大和シルフィードが育む多様性と地域の絆
【スポーツと共生社会の交差点】
6月1日、大和なでしこスタジアムに集ったのは、年齢も性別も国籍も異なる多様な人々だった。スタジアムの一角には、ボッチャやアンプティサッカー、デフサッカー、ブラインドサッカーを体験できるブースが設けられ、約30組の家族連れが集い、それぞれの競技に真剣に挑戦していた。普段はなかなか触れる機会の少ないパラスポーツを一度に体験できるこの空間には、笑顔と驚きがあふれていた。なでしこリーグの試合前には、知的障がい者サッカー女子日本代表によるエキシビションマッチが行われ、スタンドからは温かな拍手が送られた。
この日、大和シルフィードが主催したのは「インクルーシブスタジアムDAY」。誰もがスポーツを楽しめる環境をつくるという理念のもと、地域の福祉団体やパラスポーツ団体と連携して開催された一大イベントだ。クラブが掲げる合言葉は「Football For ALL」。サッカーという共通言語を通じて、人と人、まちとクラブ、障がいのある人とない人を結びつける。その姿勢は、日々の実践に裏打ちされている。
まさにこの日、大和のスタジアムは「誰もが楽しめる」インクルーシブな空間となっていた。

【スタジアムを開かれた空間に。企画に込めた想い】
「インクルーシブスタジアムDAY」と銘打たれたこのイベントには、「スタジアムをすべての人に開かれた場所にしたい」という、大和シルフィードの強い想いが込められている。
「ホームゲームは、単に試合を行うだけの場ではなく、クラブとして発信したいメッセージを届ける場でもあります」。そう語るのは、同クラブの代表取締役社長・橋本紀代子氏だ。3年前から始まったこの取り組みは、LGBTQ当事者の理解促進を図るプライドマッチや、乳がん啓発のピンクリボンデーと並び、地域社会の多様性に向き合うクラブの姿勢を象徴するものとなっている。背景にあるのは、人口約24万人を抱える大和市の実情だ。
「LGBTQ当事者は約8~10%、認知症の方は1万人、障害者手帳をお持ちの方全体の1~2割に上るとされます。ホームゲームにそうした方々も来ていただきやすい場をつくるのは、当然のことだと私たちは考えています」と橋本氏は語る。
イベント開催に至ったもう一つのきっかけは、「JFAフットボールデーインクルーシブフットボールフェスタ神奈川」に3年前から参加したことだった。そこで障がい者サッカーチームや支援団体との"横のつながり"が生まれたことが、現在の活動の礎となっている。
「このフェスタに参加したことで、障がい者サッカーチームとの関係性が築かれ、そこからサッカー教室を委託されるなど、連携が広がっていきました」
このように、地域との接点を持ち続けてきた日々の積み重ねが、今回の企画の実現を後押しした。

準備段階では、バリアフリーの課題に直面した。会場となる大和なでしこスタジアムは、設備的に古い部分も多く、特に車椅子での来場者にとって、2階へのアクセスは困難を伴う。そこで今回は、車椅子利用者や高齢者も参加しやすいよう、すべての体験ブースを1階のアクセスしやすいエリアに集約した。「我々の行動を通して、施設の改善が地域にも広がっていくよう、行政へのメッセージも込めて取り組んでいます」と橋本氏は語る。
今年のメインプログラムの一つは、知的障がい者サッカー女子日本代表と大和シルフィードアカデミーのエキシビションマッチ。これまでも連携を続けてきた関係者との信頼関係をもとに、フランクな対話の中から実現した企画だ。また、体験ブースには4団体が参加し、各ブースには約5名ずつ、総勢30名ほどが関わった。クラブが全体の枠組みを用意し、そこに「やってみたい」という声を柔軟に取り込む形を取ることで、誰もが関われるイベントとして設計されている。
【選手が体感した、「スポーツの本質」】
選手たちにとっても、特別な体験となった。トップチームの佐々木優芽は、2回目の参加となったパラスポーツ体験ブースで、松葉杖を使ったアンプティサッカーに挑戦。「本当に難しかったです。普段使わない筋肉をたくさん使って、改めてすごいなと感じました」と振り返る。
特に心を動かされたのは、体験中に出会ったパラアスリートの言葉だ。
「ドリブルがとても上手な方がいて、真似してみたけど全然できなかった。『どうしたらそんなに上手になれるんですか?』と聞いたら、"練習と努力を重ねていくことが大事"と教えてくださったんです。努力の大切さは、障がいのある、なしに関係なく共通するものだと、改めて気づかされました」

アンプティサッカーの体験を通じて、スポーツの本質的な共通点に気づいた。ボールに触れる喜び、プレーへの真剣さ──。それらはあらゆる人に通じるスポーツの魅力といえる。
「生きていく中で、一つのことに没頭できるものがあるのは素晴らしいこと。私にとってはサッカーだけど、今回出会った方々も同じように、スポーツを通じて自分の世界を広げているんだと感じました。今度は実際にアンプティサッカーの試合を見てみたい。プレーを見て、応援することで、もっと深く理解できる気がします」
この体験が、選手たちの視野を広げ、行動を変えるきっかけになるかもしれない。クラブが掲げる「Football For ALL」という理念は、選手たちの感性の中にもしっかりと根を下ろしつつある。
【誇りを胸にピッチへ 背中を押した「日本」コール】
知的障がい者サッカー女子日本代表チームにとって、なでしこリーグの前座として行われたエキシビションマッチは、特別な舞台となった。観客約100名が見守る中、選手たちは国内で初めてJFAの日本代表ユニフォームを着用し、緊張と誇りを胸にピッチに立った。

知的障がい者サッカー女子日本代表監督の稲葉政行氏は、「今回は私が代表監督をしていたこともあり、『代表として試合ができたらいいですね』というインスピレーションから実現しました」と語る。橋本紀代子社長とのつながりは、JFAフットボールデーインクルーシブフットボールフェスタ神奈川をきっかけに生まれた。
当日は公共交通機関での移動となり、「JFAのウェアとバッグで電車移動をする中、『どの代表チームだろう?』と注目されて、選手たちの自己肯定感が高まったように感じました」と振り返る。選手たちからは「このユニフォームに相応しい選手になりたい」「身震いした」「感謝の気持ちをプレーで返したい」といった前向きな声が相次いだ。
「代表である以上、勝利を目指しましたが、試合は残念ながら敗れました。ただ、セレモニーや試合中、"日本コール"で背中を押していただけたことは、選手にとって大きな刺激になったと思います。指導者としても誇りに感じる一日でした。選手からは、『質の高いプレーをするためにチームに戻って努力したい』と前向きな声が多く上がりました」

今回のイベントでは、知的障がいのある選手たちに限らず、ブラインドサッカーやアンプティサッカー、デフサッカーといった他のパラスポーツ関係者とも自然な形での交流が生まれた。JFAで障がい者サッカーのリフレッシュ講習会の講師を務める稲葉氏は、現場での実践と対話を重ねる中で、強く実感していることがある。それは、カテゴリーを越えて誰もがともにサッカーを楽しめる環境づくりが、社会にとって非常に重要な価値を持つということだ。
JFAが掲げる「アクセス・フォー・オール」の理念に基づき、障がいのみならず、女子、貧困、LGBTQ、外国人といった、サッカーの届きづらい層へもアプローチしていく必要性を強く感じているという。
「今回の取り組みが一過性のものではなく、各地でそれぞれの形として継続されていくことを願っています」
稲葉氏はそう語り、大和シルフィードとの協働が今後も継続的なものとして地域に根づくことに期待を寄せた。

【地域と歩む未来へ 継続が育む絆と広がり】
橋本紀代子社長は、今回の取り組みを通じて得た手応えと、そこに見えた課題の両方を静かに受け止めている。
「選手が関われるポイントは限られていましたが、若い選手にとっては新しい感覚だったと思います。インクルーシブなイベントに初めて触れた選手も多く、みんな本当に楽しそうでした」
そして、こうした活動に込める思いは、単発のイベントにとどまらない。
「年によっては小さな規模になることもあるかもしれませんが、まずは"続けていくこと"が大切です」と橋本氏は語る。今後は障がい者サッカーチームとの連携や、スクール活動などを通じて、ホームゲーム以外の場でも定期的に発信していけるような長期的な事業を構想しているという。
大和のまちと、クラブと、そして多様な人々をつなぐこの活動は、着実に歩みを重ねてきた。インクルーシブスタジアムをめざす挑戦は、すでに地域の中に根を張り、これからさらに広く、深くその可能性を伸ばしていこうとしている。
文=松原渓(スポーツライター)
 一般社団法人日本女子サッカーリーグ
一般社団法人日本女子サッカーリーグ